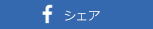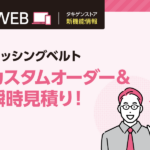日常生活から先端産業まで ― 活躍の場広げる各種粉体

配管は各種流体輸送やエネルギーを伝達
2025年1月、埼玉県八潮市で老朽化した下水道管の破損が原因で大規模な道路陥没が発生、走行中のトラック1台がのみこまれ、運転士が亡くなったことはまだ鮮明に記憶に残っています。その修復には数年を要するとさえいわれています。これだけではなく、それ以前も以後も全国各地で上下水道管の老朽化が深刻な事態を招いています。経年劣化によるものと思われますが、今後もこうした事態がそこかしこで発生する可能性は否定できず、早急な対応が求められます。
上下水道に限らず、液体や気体、粉体など各種流体の輸送やエネルギーの伝達などを目的としたシステムが配管で、パイプやホースなどの管、管継手、バルブ、計器などで構成されます。用途が広いのは流体配管で、石油のパイプラインや上下水道、都市ガスの導管などの各種インフラをはじめ、建築関連では住宅やビル、工場の給排水や空気調和に、工業分野では化学プラント工場や原子力発電所の冷却水配管などに加え、半導体や機械、自動車といった主要な産業分野でも活用されています。いずれも太さや長さなど規模から多種多様な配管があり、技術の高度化も進んできています。
配管で輸送する液体や気体は、水道水や都市ガスなどでイメージしやすいですが、粉体の輸送は分かりづらいところがあります。粉体は固体粒子が集まったもので、集まった固体粒子が互いに影響しあっていると定義されています。その上で、外力により流動性を有することが大きな特徴で、種類は非常に多岐にわたります。
粉体や粉粒体、粉体製品は幅広く活用されていますが、これらを生み出す粉体技術を構成する単位プロセスの多さも特徴です。必要とする原料となる固体を保管し、必要量を輸送・供給するハンドリング、粉体製品を生み出す〝入口〟にあたる粉砕・破砕、さらに分級・ふるい分け、混合・撹拌・分散、造粒・コーティング、計測・測定、焼成・成形などが知られています。以前は各プロセスを単独で活用することが主流でしたが、最近では複合化することで、より精細な粉体粒子や粉体製品の創製につながっています。その背景には粒子サイズの微小化があり、現在ではナノスケール(ナノは10億分の1)粒子が本格的な実用化の段階に入っています。粒子の微小化によって、医薬品の有効成分の吸収率向上や経口投与の際の飲みやすさの改善、化粧品の肌への密着性を高めているほか、電子部品の高密度化、建材の強度化・軽量化などを実現しています。

粉体を空気で運ぶ
-2種の方法を物性やサイズ、距離に応じ選択
粉体プロセスで配管を活用するのは粉体のハンドリングを担う輸送プロセスで、原料に応じて各種の方法が使い分けられています。粉体が流動性を有するため、食品原料をはじめ化学・医薬品原料、鉱産物、セメント、触媒などの輸送に主に活用されるものが空気輸送です。ブロワやコンプレッサーなどの空気源、供給部、パイプ(管路)、回収部などから構成され、一般的には空気の力で輸送しますが、空気の活用が難しい原料の場合は不活性ガスも使われます。輸送距離は数メートルクラスから3,000メートルクラスまでと幅広く、いずれも粉体特性や粒子サイズ、活用分野・場所などを踏まえた検討が重要になります。
輸送方法は低濃度輸送と高濃度輸送に大別されます。低濃度輸送は輸送媒体となるガス中に粉体を懸濁し運ぶ方法で高速搬送が可能です。輸送距離は比較的長く取れますが、高速であるがため、粉体が管路の壁にぶつかるなどして摩耗や損傷の恐れがあり、軽量な材料や摩耗・損傷しても支障のない粉体などが対象となります。連続的な輸送もでき、大量で安定した操作が実現できます。
一方、高濃度輸送は管路内に密に詰まった粉体を、輸送媒体の圧縮流れで押し出す方法で、低速で輸送されます。粉体の輸送速度が遅いことから、管路の摩耗とともに粉体の摩耗・損傷も防止できるため、低濃度輸送とは異なり、壊れやすい粉体にも適しています。少ないガス量で輸送できるメリットがある半面、大量輸送には不向きといわれる一方で、長距離輸送に適していますが、その分、設備コストが増大する可能性があるため、輸送距離は対象物質による検討が必要です。
輸送方法を的確に選択できても、粉体の特性や物性によって管路内で付着現象を起こしたり、管路壁への衝突が繰り返されたりすることで、管路の破損なども起こりかねません。特に管路の破損はシステム全体への影響も大きいため、速やかで効率的な修復、改善が必要になります。
プロセスを左右する的確な粒子の計測・制御
管路内の付着現象発生は、粒子サイズの微小化も影響しています。粒子の微小化は従来にはない性質や物性を発現、新たな展開につながる一方、付着や凝集現象などの引き金にもなります。これを防ぐには管路の材質の検討に加えて、粉粒体の的確な計測・制御が重要になります。
その実現のため、粉体粒子の物性や挙動を把握できる各種計測装置や手法が用いられますが、最近利活用が盛んなのがシミュレーション技術です。微小な粉体粒子の挙動は目視が困難で、これまでからシミュレーション技術が導入されてきました。導入当初はシミュレーション結果と実際のかい離も多く見られましたが、コンピュータやソフトウエアの急速な技術進展で精度が飛躍的に向上、今では単に粒子の物性や挙動の把握にとどまらず、粉体関連装置やシステム設計にまで応用範囲が拡大しています。
また人工知能(AI)やビッグデータ(大量データ)の導入・活用も粉体プロセス関連で進みつつあります。本格的な活用や成果はこれからですが、業界団体でもAIの理解と活用促進への取組みを活発化させています。利活用の底辺が広がれば、複雑な粉体の挙動、性質、物性のさらなる解明への武器として期待されます。
潜在力の大きさから無限の可能性秘める
研究開発が活発化する粉体プロセスにより創出される各種粉体や粉粒体製品は、小麦粉やコーヒーをはじめとした食品類のほか、医薬品や化粧品、入浴剤などは私たちの日常生活には欠かせない存在になっています。製品そのものが粉末状なので粉体という言葉は知らなくても理解しやすいでしょうが、一方で先端産業の発展にも大きな役割を果たしていることは意外に知られていないかもしれません。今ではあまり使われなくなったフロッピーディスクやカセットテープに使われていた磁性粉のほか、乾式コピーのトナーは粉体技術の結集といわれました。
最近ではカーボンニュートラル(温室効果ガス排出量実質ゼロ)の実現に大きな役割を担うといわれる次世代電池、中でも全固体電池の開発・実用化は粉体プロセスの表面改質技術がカギとなるとみられています。電解質を固体化する全固体電池で、従来の液体状の電解質に匹敵する電子の移動には優れた界面の生成が不可欠になるからです。また脱炭素化や環境・リサイクル関連でも重要な位置を占めるなど〝産業のコメ〟とも称され、その発展を影で支える大きな存在となっています。こうしたポテンシャルから、活用範囲はさらに拡大することが期待されています。

ただ一方で〝迷惑な存在〟となっているものもあります。多くの人が罹患する花粉症の原因物質のスギやヒノキの花粉、時折日本に飛来する黄砂、PM2.5、全世界を巻き込み社会・経済に大きな影響を及ぼした新型コロナウイルス。そのウイルスも粉体(粒子)の一種で、全てが有益ではないことを知っておく必要があります。これら迷惑な存在も、未知の可能性を秘めた物質であると捉え、さまざまな角度から研究が進められています。今後、有益に活用できる成果が見いだされるか注目したいところです。
[日刊工業新聞社]